令和6年度社会科・主権者教育研究交流会の開催報告

3月26・27日(木・金)に、岡山大学・埼玉大学・宮崎大学・鳴門教育大学・愛媛大学、五大学合同での社会科・主権者教育研究交流会を行いました。
当日は、岡山大学桑原敏典教授、埼玉大学小貫篤准教授、各大学の学生・院生、現場の先生が来学、また、zoomより宮崎大学吉村功太郎教授、筑波大学唐木清志教授も参加され、井上ゼミの学生と社会科・主権者教育について研究交流を行いました。
【1日目のプログラム】
はじめに、8グループに分かれ、自己紹介とアイスブレイクを行いました。また、井上先生より、本会を開催するにあたって、この五大学合同研究交流会の趣旨や本会への思いや願いなどのお言葉をいただきました。

1日目のプログラムでは、まず、「大学教員への質問タイム」が行われました。桑原敏典教授、小貫篤准教授、吉村功太郎教授、本学の鴛原進教授、井上昌善准教授へ、各大学の学生より質問が寄せられました。学生指導の際に何を意識しているのか、なぜ大学の先生を志したのか、どのような研究をされているのか、ICTをどのように学校教育において活用していくべきか、社会科教師に求められる資質・能力をどのように考えているか、学生からの多岐に渡る質問に真摯に答えていただきました。特に、最後の社会科教師に求められる資質・能力についてはそれぞれの先生から熱い言葉をいただき、教師自身が社会の一市民として生きる姿勢を持つこと、フィールドワークを積極的に行い教材研究に真摯に取り組むこと、思考し続ける体力を持っておくことなど、今後社会科教員を目指すものとして大切なことについて学ぶことができました。

次に、各大学による実践研究報告が行われました。第一に、愛媛大学チームより、日々のゼミ活動と地域と連携した出前授業・プロジェクトについて発表していただきました。まず、日々のゼミ活動についてです。個人・グループで取り組んだ教育・研究活動や、社会科教育学における書籍についての意見交換を通して、他者と協働しながら研究を進めることの重要性について述べられていました。次に、地域と連携した出前授業・プロジェクトについてです。これらの授業・プロジェクトは、「災害被害の多い土地」と共に生きる、「野生動物・自然」と共に生きる、「社会に生きる人々」と共に生きることをテーマとしており、「共生」をキーワードとして、実践を行ってきたことを報告されていました。また、報告の際には、授業構成やプロジェクトの概要だけでなく、授業を通してどのような成果と課題が明らかになったかについても述べられていました。

第二に、埼玉大学チームより、日々のゼミ活動の様子と卒業研究の構想について発表していただきました。まず、日々のゼミ活動についてです。社会科教育学に限らず、多様な学問分野について学ぶことを大切にされているというお話がなされ、そうした信念のもと、読書会やフィールドワークを実施していることについて述べられていました。次に、卒業研究の構想についてです。ジェンダー、カルチュラルスタディーズ、シンガポールの教科書分析、戦争遺跡、政治的中立性、絵本の活用、共生社会など多様な研究テーマについて報告いただきました。報告の中で、社会科教育学だけではなく他の分野の研究成果に依拠する難しさや、他国の教科書分析を行ううえでの難しさなど、研究を進めていくうえでの悩みについても共有していただきました。

第三に、岡山大学チームより、北朝鮮拉致問題やハンセン病を題材とした主権者教育の実践報告と、「消費者市民社会の構成員としての判断力育成を目指した法教育プログラム」について発表していただきました。まず、主権者教育の実践報告についてです。北朝鮮拉致問題チームとハンセン病チームそれぞれから報告いただきました。両チームとも施設訪問や研修を行っており、当事者の状況を踏まえたうえでの授業開発・実践がなされていました。また、こうした問題が主権者教育とどのように関連しているのかについても整理されており、今回取り上げた問題は唯一絶対の答えがあるものではなく、こうした社会問題を主権者教育において扱うべきであるのではないかと述べられていました。次に、法教育プログラムの実践報告についてです。消費者市民の在り方を問い直し、どのように民法を学ぶことが、事業者と消費者の情報格差を埋めることに近づくのかについて述べられていました。実践を通して、提示した問いや資料によって、こうした消費者トラブルの問題の所在を、十分に問い直すことができなかったことなどが課題として述べられていました。

第四に、鳴門教育大学チーム安藤瑞輝さんより、学社連携の取組について発表していただきました。安藤さんは、社会とのつながりが希薄となっていることに対して問題意識を抱いていることについて述べられました。そして、防災教育を事例として、大学生や地域の人たちが子どもたちと繋がることのできる教育プログラムを何度も開発・実践してきたことを報告されていました。また、今後の展望として、学校教育において学社連携を一層充実させるための方法などを明らかにしていきたいことについて述べられていました。

最後に、ここまでの発表を踏まえて筑波大学唐木清志教授よりご講評 をいただきました。唐木先生からは次の二つのことについてお話をいただきました。まず一つ目は、「探究」についてです。唐木先生は、探求にそれぞれレベルがあることを示され、子どもたちが自立して探究できるように学習を組織できるようにしていくだけではなく、大学生自身も探究のレベルを向上させることの必要性について述べられていました。探究のレベルを向上させるなかで、自分の研究が社会科教育・日本の学校教育の課題にどのように関連するのか、その位置づけを明らかにしていく必要性について述べられていました。二つ目は、社会科教師に求められる資質・能力についてです。唐木先生より、「授業で勝負できる教師になってほしい」という思いが伝えられました。そのため、社会科においてどのような資質・能力を身に付けてほしいか、教師自身が子どもとしっかり向き合い、個性のある教材研究を行うことを通して自分なりの公民的資質について考える必要性について述べられていました。

【2日目のプログラム】
午前のプログラムでは、桑原敏典教授より「外部機関との連携を通した主権者教育」という題目で講話とワークショップをしていただきました。

講話では、まず、「若者の声を政治にもっと反映させるために、日本でも選挙権年齢を18歳からさらに16歳に引き下げるべきか?」というテーマについて各班でディベートを行いました。この活動を通して、そもそも選挙とは何のために行うのか、学校教育はどのような姿勢を持って主権者教育と向き合っていくべきなのかを考えることができました。

次に、岡山県における外部と連携した主権者教育の実際について、説明していただきました。地域と連携した授業を行うにあたって、自分たちを地域の構成員として自覚させ、自分たちの地域・生活をどのようにしていきたいかということを思考させることが重要であることが事例よりわかりました。加えて、学校教師自身も地域のことを知ろうとする姿勢が重要であることについても学ぶことができました。最後に、政治的中立性に関するお話がありました。政治的中立性とは、政治的に偏りがあるとされる題材を扱わないことではなく、そうした教材に対する多様な考え方を保障する学習を展開することであると説明がありました。政治的中立性という言葉を盾に、教師の自由な教材研究は阻害されるべきでないことについても述べられていました。
以上が午前のプログラムでしたが、ここで埼玉大学の小貫篤先生よりコメントをいただきました。今日までのプログラムを通して、様々な授業観・社会観・社会科観が見えてきたこと、さらに、交流を通して個々人のそうした考え方もアップデートされた点において意義のある会であったとお話をいただきました。

午後のプログラムでは、愛媛大学チームと岡山大学チームによる松山城・道後温泉フィールドワークが行われました。各グループに分かれ、松山城や道後温泉を訪れる中で、課題として提示されていた「人口流出が課題となっている松山市において、どのような対策を行うべきか」について考えました。各チーム、最後に親睦を深めながら、どのようなところに松山の良さがあるのかについて考えることができました。特に、愛媛大の学生は普段から目にしているものであるため、岡山大の学生さんの気づきから改めて松山の良さを実感することができました。以下、フィールドワークの様子です。


フィールドワークから帰還した後は、各々が今どのような研究をしているのかについて報告し合いました。今どのような論文や書籍を読んでいるのかについて共有し合いました。中には、実際に読み進めている本を持ってきて紹介してくださる学生さんもおり、この報告会を通して、さらに研究に取り組んでいきたいという思いが高まりました。
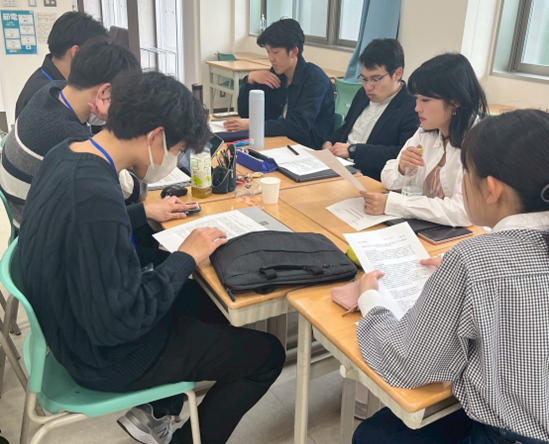
最後に、本会のご講評を桑原先生よりいただきました。同大学の研究室中だけでは、同じ研究テーマを持つ学生と出会うことは難しいですが、こうした他大学との交流する機会があることによって、研究テーマを同じとする学生と出会えたり、自分の研究室だけでは出会えないようなテーマに触れたりすることができる良さがあることについて述べられていました。

今回の研究交流会では、他大学の学生と交流を深めることで、今まで気づくことができなかった新たな視点や学びを得ることができました。また、先生方の講話より、社会科教師に求められる資質・能力についても改めて考えることができました。よりよい社会科授業づくりができる教師を目指し、より一層、研究室における教育活動・研究活動に励んでいきたいと思います。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。